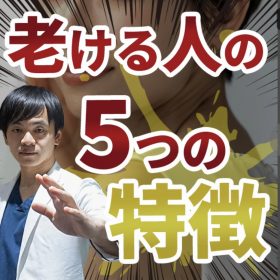新たな国民病である慢性腎臓病を予防し、健康を保つ有効な手段としては、タンパク質制限、減塩、禁煙といった生活習慣の改善が推奨されています。今回は、とくに「食生活習慣の改善」に的を絞り、以下3つのポイントをご紹介していきます。
- 抗糖化
- 抗炎症
- 抗酸化
1.抗糖化
AGEは日本語では「終末糖化産物」と呼ばれています。これは、血糖中の過剰な糖が変質を繰り返した結果、生じる物質です。AGEと結合した血管の動脈は、本来の柔軟性を失い劣化します。さらには炎症を起こし、動脈硬化を招きます。
体内のAGEを減らすためには、まず高糖質の食品を避け、血糖値を下げることです。しかしこれだけでは、十分とは言えません。同じ食品でも、作り方によってAGEの産生量は異なります。例えば、高温加熱(焼く、炒める、揚げる)で調理された食品では、AGE量が爆発的に増えることがわかっています。鶏胸肉は、焼いた、あるいは揚げた場合には、茹でた場合に比べて、AGEは4~5倍も多く産生されます。食品の種類だけではなく、作り方にも注意が必要なのです。
2.抗炎症
一般的な動脈硬化のリスク因子(喫煙や肥満など)以外にも、リスク因子が存在することが、最近の研究でわかってきました。体の中に発生する「慢性炎症」もその一つです。
慢性炎症とは、体内で静かに進行する炎症です。一般的に炎症は、私たちを外敵から守ってくれる免疫システムです。しかし、現代の生活習慣や環境の変化で、炎症の慢性化が進みました。結果、炎症は「味方」ではなく「敵」になってしまったのです。
さて、この慢性炎症を悪化させる食事としては、精製された炭水化物(一般的なパンやパスタ)が有名です。そのほかにも、フレンチポテトなどのフライ類、ソーダに代表される砂糖が豊富な飲み物などがあります。一方で、慢性炎症を改善する、いわゆる「抗炎症」の作用がある食事としては、魚(サーモン、マグロ、サバなど)が有名です。そのほかにも、果物(リンゴ、ブルーベリー、チェリーなど)や緑色野菜、ナッツ類などがあります。つまり、より自然で、かつ精製されていない食事が、慢性炎症改善や動脈硬化予防に有効とされています。
3.抗酸化
私たちの身体は、酸素を利用してエネルギーを作り出しています。酸素を利用すると同時に、常に活性酸素が体内で生じています。この活性酸素(酸化ストレス)は、私たちの細胞を傷つけ、さまざまな疾患をもたらす元凶となっています。とくに活動量の多い腎臓では、活性酸素が多くなっているといわれています。もちろん、私たちの体内には、活性酸素から身体を守るシステムが備えられています。しかし、このシステムの機能は加齢とともに低下します。結果、活性酸素の量が過多となってしまうのです。
抗酸化作用に富んだ栄養素には、ビタミンC、Eやポリフェノールなどがあります。ビタミンCは緑黄色野菜や果物に、ビタミンEはナッツ類に多く含まれています。また、コーヒー、緑茶や紅茶などには、ポリフェノールが多く含まれています。これらの食材を意識して摂り入れてみてください。
慢性腎臓病を予防できる運動生活習慣
確かに、一昔前はCKD患者さんは尿蛋白が増えて腎機能に悪影響が及ぶため「安静が第一」とされていました。
しかし、現在ではその考え方は変わってきています。実際に最新の研究では「有酸素運動を取り入れたCKD患者さんは、行っていない患者さんと比べ腎機能が改善した」との報告もあります。また、別の臨床研究でも「ウォーキングを行ったCKD患者さんは行わなかった群と比較し、透析への移行が2年ほど先延ばしできた」との報告もあります。透析になった場合でも、定期的な運動習慣のある透析患者さんは定期的な週間がない透析患者さんよりも生命予後がよかったとの報告もあります。実際にアメリカのガイドラインでも「医療関係者は透析患者の運動能評価と運動の推奨を積極的に行う必要がある」と明記されています。
よって、現在ではCKD患者さんには毎日の20-30分のウォーキングと週数回の簡単な筋トレを推奨しています。
皆さまに伝えたいこと
「食生活習慣の改善」の3つのポイント及び運動習慣はいかがでしたでしょうか? 腎機能低下を予防するためには、何よりもまず減塩が第一であることはもちろんです。減塩ができた後に、今回紹介したポイントを、ふだんの生活の中で意識してみてください。