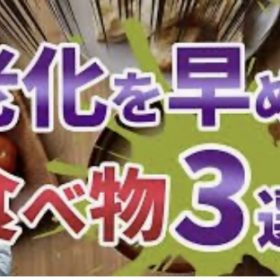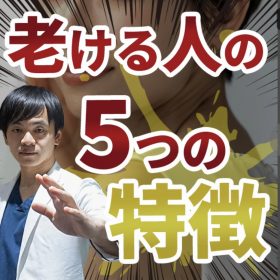前回は古典的な危険因子(肥満、喫煙、高血圧など)以外にも体の中に発生する“慢性炎症”が動脈硬化、心筋梗塞や脳卒中などの新たな危険因子であることを皆さまと共有しました。
今回はどういった生活習慣が慢性炎症を抑えれるかをお伝えしていきます。
全身の慢性炎症がおこりやすい生活習慣
①炭水化物(糖質)の過剰摂取
摂取した糖質の量が多すぎると、血液中のグルコース(ブドウ糖)が過剰になります。そして過剰のグルコースは細胞や組織のたんぱく質と結びつき、「糖化」が起こります。糖化されたたんぱく質はAGEsになります。このAGEsが様々な臓器障害や全身の炎症を引きおこすといわれています。
②飽和脂肪酸の過剰摂取
一般生活者20人に、飽和脂肪酸の多い食事か、または不飽和脂肪酸の多い食事を、8週間続けてもらう研究がオランダで行われました。その結果、飽和脂肪酸の多い食事をした群では、脂肪組織で炎症に関わる遺伝子が多く発現していました。つまり、炎症が起きている、または起きやすい体になっていることを示しています。
③過剰な塩分摂取
高血圧の人を対象に行った研究では、食塩の摂取が多いほど炎症マーカーの一つであるCRPが高いとの結果がでており、過剰な塩分接種は体内で慢性炎症が進行させている可能性があります。
他にも喫煙や運動不足が全身の慢性炎症と関係していることが多くの過去の研究で報告されています。
慢性炎症を下げる生活習慣
基本的には適切な食事と運動をすることが重要です。それに加えて、下記の食生活も慢性炎症を下げるのに有効と考えられています。
①オメガ3脂肪酸の摂取
東北地方の男女14,191人を対象に行った研究では、食品中に含まれるオメガ3脂肪酸が多い人は少ない人比較し、全身の炎症値を示すCRPがというマーカーが低い結果がでました。この関係性は男性喫煙者群でより明確に観察されました。
| オメガ3系脂肪酸の多い食物 オメガ3脂肪酸はえごま油、シソ油、亜麻仁油、くるみ、チアシード、グリーンナッツオイル、青魚(サバ・イワシ・アジ・マグロ、サーモンなど)緑黄色野菜、豆類などの食品に含まれています。 更にオメガ3系脂肪酸の多くとると、心筋梗塞や動脈硬化になりにくく、喘息などのアレルギー性疾患の予防、将来の認知症予防などの効果もあるといわれています。 つまり、現代人は慢性炎症さげるとことは関係なくオメガ3系脂肪酸が豊富な食事を多くとるべきなのです。 |
②適度な運動
運動は体内の炎症を下げることが期待されています。
数千人を対象にして研究では、軽い運動を週1回以上行う人は体内の炎症値が低かったことがわかっています。
まとめ
慢性炎症は動脈硬化疾患の共通した発症リスクであります。慢性炎症を上げないような生活習慣を意識することがアンチエイジング及び健康への第一歩であります。
| 参考文献 Interleukin-6 Level among Shift and Night Workers in Japan: Cross-Sectional Analysis of the J-HOPE Study. J Atheroscler Thromb. 2018 (in press) |