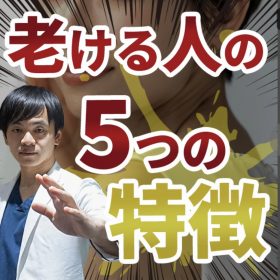・Framingham研究
1948年、マサチューセッツ州フラミンガム市(人口28,000人)で心血管疾患・合併症に先行する因子の同定を目的とする大規模な臨床研究が行われました。
この結果以下の6因子が心血管疾患・合併症の危険因子であることが分かりました。
①高血圧
②脂質異常症
③肥満
④糖尿病
⑤喫煙
⑥ストレス
言い換えると、この試験が行われるまでは肥満も喫煙も心血管疾患の危険因子であることは知られていなかったのです。この6つに加え、現代では更に⑦慢性腎臓病と⑧高尿酸血症も心血管疾患の危険因子であると考えられています。
文化の近代化とともに高尿酸血症が問題になってきています。中国において2001年から2017年までには高尿酸血症の有病率は2.5倍にも増大しています。
適正な尿酸は有益、過剰な尿酸は有害
尿酸自体に、さまざまな疾患をもたらす元凶である酸化ストレスから、我々の体を守ってくれる作用や神経保護作用もあることも分かっています。実際に尿酸が低いケースでは認知症になるリスクが高くなるといった報告も認められています。
しかし、尿酸は、7.0mg/dLまでが基準値内でありますがこれを超えると異常とされ、高尿酸血症と呼ばれます。血中の尿酸値が7.0mg/dLを越えてしまうと、関節内に尿酸が溜まってしまうためです。
尿酸が高いとなぜいけないのかというと、高尿酸血症のリスクは痛風だけではなく、心血管疾患や慢性腎臓病など、動脈硬化に関連した疾患のリスクであるからであります。
実際に沖縄県の一般住民48,177人を対象として研究では、高尿酸血症がある場合の末期腎不全にいたるリスク(腎機能が低下し透析になってしまうリスク)は男性4倍、女性9倍にも高くなることが分かっています。
高尿酸血症の予防
高尿酸血症の原因は遺伝的要素もありますが、生活習慣にも依存するものです。
産生過剰型のケースでは、高プリン食(肉類/魚介類など)やビールなどのアルコールの摂取、また果糖の過剰摂取などが原因であると考えられています。高尿酸血症の方はこれら食生活の見直しが推奨されます。
尿酸の尿中への排泄低下の原因もまた、生活習慣にあります。
肥満や糖尿病によるインスリン抵抗性(インスリンが効きにくい状態)やアルコールが原因であると考えられているのです。
プリン体が入っていないアルコール(焼酎など)の摂取でも尿酸値が上がる可能性がありますので、注意しておいてください。
| 参考文献 ・Iseki K et al: Am J Kidney Dis 44:642, 2004 |